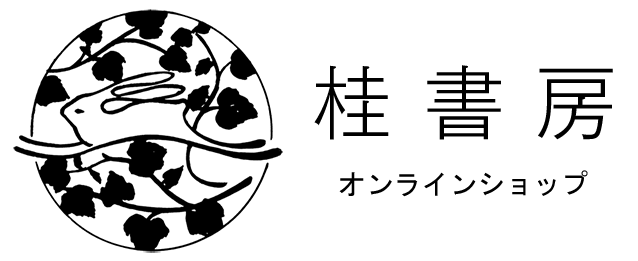-

輪島朝市 人々の生業と暮らし
¥2,860
80〜90年代におこなわれた輪島朝市の調査を加筆しまとめた一冊。輪島朝市をとりまく人々の暮らしや生業、土地に根付く文化の記録と、当時の朝市通りの情景や売り手のおばちゃんらの写真を豊富に掲載。さらに、能登半島地震後の出張輪島朝市も調査し、メディアではいかなる切り口で能登が報道されていたのかを考察する。 編 者:溝口常俊 定 価:¥2600(税込:¥2860) 発行日:2025.12.26 ISBN:978-4-86627-172-9 判 型:B5判 頁 数:168頁 ●目次 はじめに 第1部 輪島朝市の盛衰 1章 朝市の歴史 2章 震災前の朝市調査 3章 震災後の復活出張朝市(2025年4月) 4章 全国の朝市 第2部 輪島朝市をとりまく周辺地域の生業と文化 5章 輪島朝市と鳳至川流域の村の変化 ―観光化と野菜栽培地 6章 小都市周辺農村における下肥利用 ―昭和初期の輪島市を事例として 7章 輪島町塗師の経済行動 ―生活史としての位置づけ 8章 輪島崎における古民謡「まだら」の伝承 第3部 生き延びるための能登半島 9章 震災後1年半の能登半島に関する新聞記事 10章 2025年4月の奥能登景観 おわりに 編者・執筆者紹介

-

中世「村」の登場—加賀国倉月荘と地域社会
¥2,970
中世後期に出現した「村」社会。その成り立ちには荘園制における領有主体の多元化が関係していた。外部諸勢力の関与、「郡」や「庄」等の制度的枠組とも重なり合うなか「村」はどのように織られていったのか。「村」を〈一個の交渉主体〉として捉え直し考察。 著 者:若林陵一 定 価:¥2700 発行日:2023.10.23 判 型:A5 頁 数:232 頁
-

地域の歴史から学ぶ 〜砺波散村を中心に〜
¥1,650
散村地域の形成は中世末から近世にかけてと言われる。 肝煎の「過去記」で知る政治と土地開発。義倉にみる飢饉対策は、今日の食糧危機への対応を考えさせられる。 幕末から現代まで、身近な地域の歴史から読み解く未来へのメッセージ。 著 者:中明文男 定 価:¥1500 発行日:2022.08.30 ISBN:978-4-86627-122-4 判 型:A5判 頁 数:156 頁
-

地域統合の多様と複合
¥3,960
一六・一七世紀という時代の意義を、中世・近世の大転換とみるのか、近世・近代へと歩み始めた時代とみるか、一定の見通しをもって列島各地で地域研究を進めるべきではないかという認識で始まった北陸中世近世移行期研究会の七年間の研究成果である。 一六・一七世紀の日本列島では、大名領ごとの地域国家形成と国郡単位の一揆による地域統合の動きが厳しく対峙したが、一方で在地・庶民のもとめもあって双方の融合や連携・協調の動きもおきた。それが織豊政権による天下統一、徳川幕府による近世国家確立を促す要因の一つともなった。北陸地域でこうした地域統合のうねりが、どのような矛盾・対立あるいは協調・連携のなかで生じ、「近世」的統合もしくは近世的支配に帰結したのか。一六・一七世紀に対象を絞り、地域統合の様相を「多様と複合」という視点から、一〇名の中世史・近世史の研究者が検討。 著 者:北陸中世近世移行期研究会編 定 価:¥3600 発行日:2021.12.20 ISBN:978-4-86627-108-8 判 型:A5 頁 数:423 頁
-

さよなら、桂
¥1,650
SOLD OUT
五箇山の最深部、桂という小村の分校に赴任した教師の、ダム建設による1970年の離村まで村人と交流し村の最後を看取った手記。山村において村人が豊かな関係を結び合い、しかも個を生き生きと生きていたことに驚く。 著 者:寺崎 満雄 定 価:¥1500 発行日:2004.12.08 ISBN:978-4-905564-79-4 判 型:A5変判 頁 数:210 頁
-

黒部奥山史談
¥3,300
加賀藩山廻り役の「奥山日記」を紹介し、明治初期の登山史の中から小杉復堂・山田珠樹・ウエストンらの新事実を語り、山案内人列伝として助七・瀬川栄吉・塚本繁松らを初登場とさせ、黒部開拓史の全貌と秘められた山道を古図と記録で明らかにする北ア山岳文化史。山名由来記や有峰古図の検討など含蓄溢れる文に貴重写真を多数添えた好著。 --- 著 者:湯口康雄 定 価:¥3000 発行日:1992.11.20
-

越中 福光麻布
¥1,980
富山県砺波平野では古くから麻を栽培し麻布を織りこれを大きな産業としていた地域であった。福光の山間地では野良着として麻布を織っていた。福光では麻布を「あさぬの」と呼ぶ。古代では布とは麻布を指していた。麻布を生んだ福光は、奈良時代に泰澄によって開山されたという医王山の東麓に広がる地域である。医王山北麓の小矢部市八講田では、八講布または五郎丸布として麻布が織られていたという。そして麻布は江戸時代には加賀藩の御用達となり城端の絹とともに福光の麻布が大きな産業となり地域を支えていた。 江戸時代に入り加賀藩は絹と麻布を藩の特産品として販売を始める。そして高岡・戸出が麻布の集散地であったが、江戸後期には福光が麻布の集散地となり福光麻布と呼ばれるようになった。福光麻布であるが、地域で栽培されたカラムシや大麻の茎の繊維を主原材料として糸を積み、織機に座して腰で編む「いざり機」と呼ばれた地機で織っていた。やがて時代は移り化学繊維が登場し、さらには戦後、大麻の栽培が禁止されたこともあって、福光麻布は昭和天皇の大葬の礼での供給を最後として廃絶してしまった。 南砺市小院瀬見では廃絶したいざり機を復刻するプロジェクトが進められているが、本著ではこの経緯を記録し保存し麻布を通じて南砺市の文化再発見を目指している。 著 者:福光麻布織機復刻プロジェクト 定 価:¥1800 発行日:2016.12.25 ISBN:978-4-86627-019-7 判 型:四六版 頁 数:192 頁