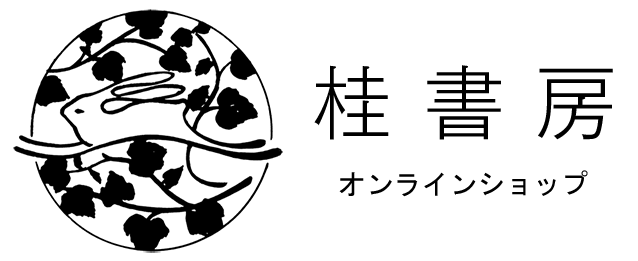-

輪島朝市 人々の生業と暮らし
¥2,860
80〜90年代におこなわれた輪島朝市の調査を加筆しまとめた一冊。輪島朝市をとりまく人々の暮らしや生業、土地に根付く文化の記録と、当時の朝市通りの情景や売り手のおばちゃんらの写真を豊富に掲載。さらに、能登半島地震後の出張輪島朝市も調査し、メディアではいかなる切り口で能登が報道されていたのかを考察する。 編 者:溝口常俊 定 価:¥2600(税込:¥2860) 発行日:2025.12.26 ISBN:978-4-86627-172-9 判 型:B5判 頁 数:168頁 ●目次 はじめに 第1部 輪島朝市の盛衰 1章 朝市の歴史 2章 震災前の朝市調査 3章 震災後の復活出張朝市(2025年4月) 4章 全国の朝市 第2部 輪島朝市をとりまく周辺地域の生業と文化 5章 輪島朝市と鳳至川流域の村の変化 ―観光化と野菜栽培地 6章 小都市周辺農村における下肥利用 ―昭和初期の輪島市を事例として 7章 輪島町塗師の経済行動 ―生活史としての位置づけ 8章 輪島崎における古民謡「まだら」の伝承 第3部 生き延びるための能登半島 9章 震災後1年半の能登半島に関する新聞記事 10章 2025年4月の奥能登景観 おわりに 編者・執筆者紹介

-

人は何を手放さなかったか 佐伯安一が観た富山の情景
¥3,300
富山民俗研究の第一人者である佐伯安一が遺した写真集。 70年にわたって富山県内各地を跋渉し、庶民の暮らしをみつめ、人々の思いに耳を傾けながら撮影された写真には、人々が守り手放さなかったものが写る。昭和20年代から平成にかけて撮影された富山の情景を氏の解説とともに400枚収録した。 方言や民具、民家、郷土料理、年中行事といった民俗研究の学説に大きな影響を与えた、佐伯安一の調査活動の集大成。 編 者:尾田武雄 定 価:¥3000(税込:¥3300) 発行日:2025.12.15 ISBN:978-4-86627-173-6 判 型:A5判 頁 数:324頁 ●目次 監修にあたって 中井精一 佐伯塾で太田学を学ぶ 安念幹倫 第1章 ムラの情景 第2章 マチの情景 第3章 山の情景 第4章 五箇山の情景 第5章 海の情景 第6章 獅子舞の情景 あとがき 平成の大合併前の市町村区分 引用文献一覧

-

戦国期越中真宗教団史論
¥3,850
金龍教英遺稿集 各門流の地域的偏差、諸寺の類型分け、消息法語の分別など新しい分析手法と多数の新史料の発掘で著名な師の史論から、論点・視点・切り口が後学の者に影響を及ぼし得る十編を厳選、史料遍を付して一冊に。真宗史研究者には必携。 著 者:金龍 静 定 価:¥3500 発行日:2025.11.10 ISBN:978-4-86627-170-5 判 型:A5 頁 数:320 頁

-

富山の近世・近代
¥4,400
圧巻は藩の「財政欠陥」の部。天保期に全国四位の借金藩となり、出入りのあらゆる富裕者に借財、踏み倒していく有様の詳述。近代越中人の「アジア認識」について検討する部も刮目。広瀬淡窓や平田派門人、江戸の藩屋敷も初紹介。 著 者:栗三直隆 定 価:¥4000(税込:¥4400) 発行日:2025.07.11 ISBN:978-4-86627-167-5 判 型:A5 頁 数:446頁

-

社会を変革する科学・技術 その歴史と未来への指針
¥3,960
人工知能などさまざまな科学分野で研究が急速に発展する現代に生きる私たちは、科学・技術の歴史を改めて辿る必要があるだろう。 本書は「社会に大きな変革をもたらす科学・技術とはどのようなものか?」を主題として、古代ギリシアから20世紀までの人物や事例の中に、その答えを見出そうと試みた。科学者たちの生い立ちと人物像、それらを通した科学・技術の成立過程を示し、2500年にわたってバトンが繋がれてきた科学・技術の歴史を描く。 これらを辿ったあとに見えてくる、現在そして将来の科学・技術のあり方、科学者の倫理について考察する。 豊富な参考文献と索引も収録し、科学・技術の歴史を学ぶ入門としてもおすすめしたい。 著 者:川越 誠 定 価:¥3600 発行日:2025.05.23 ISBN:978-4-86627-162-0 判 型:B5 頁 数:510 頁 ●目次 はじめに 第1章 科学・技術と工学 第2章 ピュタゴラスとプラトン 第3章 アリストテレスとプトレマイオス 第4章 コペルニクス 第5章 ケプラーとガリレイ 第6章 ニュートンとフック 第7章 産業革命と蒸気機関 第8章 ダーウィン 第9章 オッペンハイマー 第10章 フォン・ブラウン 第11章 チューリング 第12章 ワトソンとクリック 終章 社会を変革する科学・技術 あとがき 参考文献 人名索引 事項索引

-

洛中洛外図屏風 勝興寺本
¥2,970
勝興寺蔵の重要文化財「洛中洛外図」屏風は、慶長八年修築後の二条城を描く洛中洛外図屏風の中で、一双が揃って現存する最古の作品である。 勝興寺門前に生まれた著者が、建築士の目線から「洛中洛外図屏風」の多くのモチーフを読み解く。 著 者:針山康雄 定 価:¥2700 発行日:2024.12.13 ISBN:978-4-86627-156-9 判 型:B5 頁 数: 136頁
-

我が百姓の一年
¥1,100
かつて人の暦は米を作ることから始まり、長い歴史の積み重ねで今日の姿になった。 大きく変化した米作りや年中行事、百姓の暮らしをイラストと共に描き、 いまとなれば歴史の一コマとなった、五十年前の百姓の姿を綴る。 著 者:湯浅直之 定 価:¥1000 発行日:2024.11.01 ISBN:978-4-86627-154-5 判 型:A4 頁 数:62 頁
-

若狭中世城郭図面集Ⅱ
¥4,400
北陸中世城郭図面集総仕上げの図面集である。 対象地域は若狭西部(小浜市・おおい町・高浜町)及び補遺編(福井県)で、73城を取り上げる。 若狭守護武田氏代々の居城後瀬山城や、在地領主の城でありながら優れた石垣を持つ白石山城、礎石建物を多数備えた石山城等多くの貴重な城郭を紹介。また新発見の城郭も記載する。さらに特別論文は、若狭中世城郭が優れた城郭だったことを立証している。若狭中世城郭を見直す城郭研究者必読の一冊といえよう。 著 者:佐伯哲也 定 価:¥4000(税込:¥4400) 発行日:2024.02.26 ISBN:978-4-86627-150-7 判 型:A4 頁 数:210 頁
-

元禄の「グラミン銀行」
¥2,200
—加賀藩「連帯経済」の行方 元禄10(1697)年、貧民に無担保で金を貸す仕法を開始、日用人たちの米の共同購入、米価高騰期に移出船が港町に米の一部を置いていく仕法と三つの実践が200年維持された加賀藩新川郡の〈社会的連帯経済〉を初報告。 著 者:勝山敏一 定 価:¥2000 発行日:2023.11.10 判 型:四六 頁 数:210 頁
-

中世「村」の登場—加賀国倉月荘と地域社会
¥2,970
中世後期に出現した「村」社会。その成り立ちには荘園制における領有主体の多元化が関係していた。外部諸勢力の関与、「郡」や「庄」等の制度的枠組とも重なり合うなか「村」はどのように織られていったのか。「村」を〈一個の交渉主体〉として捉え直し考察。 著 者:若林陵一 定 価:¥2700 発行日:2023.10.23 判 型:A5 頁 数:232 頁
-

私が聞いた福光の昔話
¥990
著者は、南砺市舘(福光町)で生まれ育った。そしてこの地域の戦中戦後、近隣の人達から聞き取った「昔話」の中から愉快な逸話を拾い上げ、温かみのある挿絵を入れて本著とした。文章も福光の方言を交えた話し言葉とし、読みやすくするため文字も大きくした。 著 者:湯浅 直之 定 価:¥900 発行日:2023.10.12 判 型:A4 頁 数:63 頁
-

黒三ダムと朝鮮人労働者
¥2,200
SOLD OUT
—高熱隧道の向こうへ 前作『黒部・底方の声—朝鮮人労働者と黒三ダム』(1992年刊)が2023年に韓国語翻訳される。その続編として黒三ダムと朝鮮人の現在を記す。 過去を変えることはできないが、二つの国の未来は変えられる?!——昨今の日韓関係のなかで、見つめ直す歴史と今。この本は、平和を願う人々の希望によって生まれた。 著 者:堀江節子 定 価:¥2000 発行日:2023.07.15 判 型:A5 頁 数:232 頁
-

越中史の探求
¥2,640
「古代」蚕の真綿が400年も越中特産だったこと、中世飢餓により「立山」地獄が焦点化された様子、「富山近代化」国への建白のほとんどが20代青年であったなど、山野河海に恵まれた越中史の異彩部を発掘する新稿を含む12論文。 著 者:城岡朋洋 定 価:¥2,400 発行日:2023.5 判 型:A5判 頁 数:310 頁
-

加賀百万石御仕立村始末記
¥2,200
「御仕立村」とは飢饉等で立ち行かなくなった村を再建するための加賀藩の善政ともいえる政策のことである。かつて砺波郡広瀬舘村の肝煎だった湯浅家に、広瀬館村が天保の飢饉で立ち行かなくなった際、加賀藩が広瀬舘村を救済するためとった政策の一部始終の書類が残されていた。著者はこの資料を7年間かけて解析し、あわせて鎌倉時代から近代までの広瀬館村の歴史を明らかにした。 著 者:一前悦郎 湯浅直之 定 価:¥2,000 発行日:2023.5 判 型:A5判 頁 数:241 頁
-

加賀藩研究を切り拓くⅡ
¥4,400
本書は、木越隆三氏の古稀記念論文集である。 木越氏の論稿とその趣旨に賛同された17名の寄稿論文からなり、加賀藩の政治や経済、文化・社会に関する論考のほか、加賀前田家にゆかりの深い人物の事績に関する論考を収録。 著 者:木越隆三[編] 定 価:¥4,000 発行日:2022.11 判 型:A5判 頁 数:473 頁
-

「平安時代」の弁官補任の整理
¥11,000
先編著『「平安時代」を読む』の【弁官】の項の相当部を、先行の刊行史料および当該期の史資料などを対校・整理しながら、各年の左・右、大・中・少、権弁を逐次掲出し、単独刊行。 平安遷都年(794)から源氏挙兵年(1180)までの弁官構成とその階位・兼官・年齢等々の諸情報を概観する、「平安時代」史研究のための座右の書。 利便を考えて「弁官」編年目次を掲載! 【関連書籍】 『「平安時代」を読む』(全4巻) http://www.katsurabook.com/booklist/1225/
-

地域の歴史から学ぶ 〜砺波散村を中心に〜
¥1,650
散村地域の形成は中世末から近世にかけてと言われる。 肝煎の「過去記」で知る政治と土地開発。義倉にみる飢饉対策は、今日の食糧危機への対応を考えさせられる。 幕末から現代まで、身近な地域の歴史から読み解く未来へのメッセージ。 著 者:中明文男 定 価:¥1500 発行日:2022.08.30 ISBN:978-4-86627-122-4 判 型:A5判 頁 数:156 頁
-

妙好人が生きる ―とやまの念仏者たち
¥2,200
禅学者・鈴木大拙が「妙好人の筆頭」と称えた、赤尾の道宗をはじめ、現代まで富山県からは脈々と妙好人が輩出した。 その実績を歴史編と資料編に分け確実な文献にもとづき紹介しつつ、妙好人の現代的意義を考察する。 著 者:森越 博 定 価:¥2000 発行日:2022.07.07 ISBN:978-4-86627-118-7 判 型:A5 頁 数:331 頁
-

石垣から読み解く富山城
¥1,430
120万石を統べる近世最大の大名前田利長が築いた富山城。 巨石5石を配した圧巻の石垣は、富山藩の改修を経て、富山城址公園に残る。 本書は、解体修理工事や発掘での新知見を踏まえ、石垣の散策に必携のカラー案内書。 著 者:富山城研究会 定 価:¥1300 発行日:2022.07.07 ISBN:978-4-86627-119-4 判 型:B5 頁 数:100 頁
-

地域統合の多様と複合
¥3,960
一六・一七世紀という時代の意義を、中世・近世の大転換とみるのか、近世・近代へと歩み始めた時代とみるか、一定の見通しをもって列島各地で地域研究を進めるべきではないかという認識で始まった北陸中世近世移行期研究会の七年間の研究成果である。 一六・一七世紀の日本列島では、大名領ごとの地域国家形成と国郡単位の一揆による地域統合の動きが厳しく対峙したが、一方で在地・庶民のもとめもあって双方の融合や連携・協調の動きもおきた。それが織豊政権による天下統一、徳川幕府による近世国家確立を促す要因の一つともなった。北陸地域でこうした地域統合のうねりが、どのような矛盾・対立あるいは協調・連携のなかで生じ、「近世」的統合もしくは近世的支配に帰結したのか。一六・一七世紀に対象を絞り、地域統合の様相を「多様と複合」という視点から、一〇名の中世史・近世史の研究者が検討。 著 者:北陸中世近世移行期研究会編 定 価:¥3600 発行日:2021.12.20 ISBN:978-4-86627-108-8 判 型:A5 頁 数:423 頁
-

大本営派遣の記者たち
¥1,980
「戦争がいけない」と言えるのは始まる日まで―東京新聞記者の著者 (1912~95) は1941年末、 陸軍報道班員としてマレー戦線へ派遣されるや、 シンガポール陥落など日本軍賛美の記事を送るしかなかった。 井伏鱒二らの横顔を交え赤裸々に戦中の自己を綴る。 戦後は富山で反戦記者魂を貫く。 --- 著 者:松本直治 定 価:¥1800 発行日:1993.12 判 型:A5判 頁 数:220 頁
-

蟹工船の記憶 -富山と北海道-
¥2,640
ある日、手元に届いた一枚の手紙。そこに貼られていた蟹工船の切手を眺めてふと思い出したのは、押入れに仕舞われていた大叔父の日記だった。彼が乗船していた富山水講初代練習船・高志丸は、大正6(1971)年に世界で初めて海水使用カニ缶を製造したという。 日記をきっかけに紐解かれる、富山における蟹工船の歴史。人類とカニ缶詰の関わりに、次々と知る越中富山と北海道の深いつながり。小林多喜二の描いた『蟹工船』から考える、富山の工船・エトロフ丸で起きた事件。そしてシュムシュ島(千島列島)への上陸。 いくつもの偶然の出会いが重なって、導かれたものは何だったのか。海を渡った人々の生きた痕跡を辿り、行き着いた先とは。 労働問題としても象徴される蟹工船に旅情的視点から向き合い、過去と現在が結んだ縁の行方を旅する新しい一冊。 著 者:橋本 哲 定 価:¥2400(税込:¥2640) 発行日:2022.05.10 ISBN:978-4-86627-113-2 判 型:B5変 頁 数:237 頁
-

さよなら、桂
¥1,650
SOLD OUT
五箇山の最深部、桂という小村の分校に赴任した教師の、ダム建設による1970年の離村まで村人と交流し村の最後を看取った手記。山村において村人が豊かな関係を結び合い、しかも個を生き生きと生きていたことに驚く。 著 者:寺崎 満雄 定 価:¥1500 発行日:2004.12.08 ISBN:978-4-905564-79-4 判 型:A5変判 頁 数:210 頁
-

孤村のともし火
¥1,320
1939~43年、飛騨山中を診療で廻った医師の三つの探訪記。加須良(白川村)では痛切な幼子の弔い話、山之村(阿曽布村)では民俗も探訪、杣が池(高根村)では伝説を詳しく紹介。ほかに民間療法と熊の膽の話。写真満載。 著 者:海野 金一郎 定 価:¥1200 発行日:2005.04.29 ISBN:978-4-903351-06-8 判 型:A5変判 頁 数:166 頁