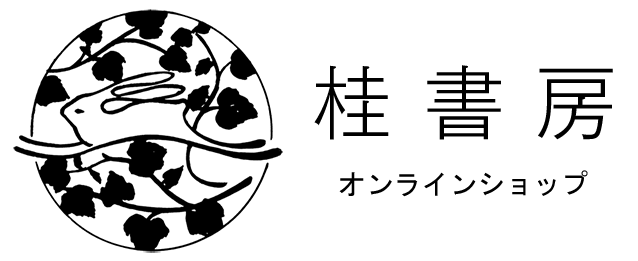-

人は何を手放さなかったか 佐伯安一が観た富山の情景
¥3,300
富山民俗研究の第一人者である佐伯安一が遺した写真集。 70年にわたって富山県内各地を跋渉し、庶民の暮らしをみつめ、人々の思いに耳を傾けながら撮影された写真には、人々が守り手放さなかったものが写る。昭和20年代から平成にかけて撮影された富山の情景を氏の解説とともに400枚収録した。 方言や民具、民家、郷土料理、年中行事といった民俗研究の学説に大きな影響を与えた、佐伯安一の調査活動の集大成。 編 者:尾田武雄 定 価:¥3000(税込:¥3300) 発行日:2025.12.15 ISBN:978-4-86627-173-6 判 型:A5判 頁 数:324頁 ●目次 監修にあたって 中井精一 佐伯塾で太田学を学ぶ 安念幹倫 第1章 ムラの情景 第2章 マチの情景 第3章 山の情景 第4章 五箇山の情景 第5章 海の情景 第6章 獅子舞の情景 あとがき 平成の大合併前の市町村区分 引用文献一覧

-

日本龍紀行 龍の細道
¥2,970
辰年生まれの著者が、山岳・河川・湖沼・瀑布・海岸・名勝など自然の地と、社寺・史跡など人工の地で「龍」「竜」の名を持つ場所を全国巡った紀行文。読んでいると実際に自分も行ってみたくなる著者の現地での体験がつまった一冊です。 著 者:村田千晴 定 価:¥2700(税込¥2970) 発行日:2025.09.15 ISBN:978-4-86627-169-9 判 型:A5 頁 数:264頁

-

富山の食と日本海
¥3,080
本書は山から海に至る多様な生態環境にある富山の食に焦点をあて、自然・文化・歴史に応じて多様な食の展開を日本海という広がりのなかで記述する。そして、未来の食の在り方についての展望を次世代に向けて提案する。 著 者:秋道智彌・中井精一・経沢信弘 編 定 価:¥2800 発行日:2025.08.25 ISBN:978-4-86627-168-2 判 型:B5 頁 数:204 頁

-

小矢部川上流域の人々と暮らし
¥3,960
かつての山村や農村での自給自足の生活や人と自然の共生、先人から受け継がれてきた民俗や習俗は、未来の日本に必要な知識である。 本書は、著者が小矢部川上流域の「刀利」と「立野脇」の各村を対象として二十余年にわたる現地調査の集大成。両村に住む人々から聞き取った昭和三十年代を中心とした、信仰、植物利用、民具、生活誌、食生活、年中行事など様々な村の暮らしを記録する。 著 者:加藤享子 定 価:¥3600 発行日:2024.10.31 ISBN:978-4-86627-157-6 判 型:B5変判 頁 数:452 頁

-

我が百姓の一年
¥1,100
かつて人の暦は米を作ることから始まり、長い歴史の積み重ねで今日の姿になった。 大きく変化した米作りや年中行事、百姓の暮らしをイラストと共に描き、 いまとなれば歴史の一コマとなった、五十年前の百姓の姿を綴る。 著 者:湯浅直之 定 価:¥1000 発行日:2024.11.01 ISBN:978-4-86627-154-5 判 型:A4 頁 数:62 頁
-

翻刻・脚注『白根草』
¥1,650
『白根草』は、昭和11年に石川県図書館協会より刊行された『加越能古俳書大観』の「解説」で日置謙氏に「加越能古俳書大観中現存の最古のものである」とされ、延宝8年(1680)に神戸友琴によって編纂された。現在まで『白根草』より古い「加越能の俳書」は発見されていない。『加越能古俳書大観』に翻刻された『白根草』は一部であり、本書で翻刻・脚注される「白根草 上」は、編者大西紀夫氏が2015年に入手された、これまで未出現だったものである。 --- 編 者:大西紀夫・綿抜豊昭 発行日:2023.07.20 判 型:B5 頁 数:80 頁
-

能登の宗教・民俗の生成
¥2,750
本書は、近世に離山した石動山大蔵坊の里修験が在地の信仰生活にいかに根ざして影響を与えたかを考察する(鏑木)。日露戦後から1930年代までに能登に関して著された郷土研究のうち、宗教と民俗に関する言説を考察する(由谷)。口能登・氷見(富山)でみられる嫁が親の死去後に実家の檀那寺で行われる「コンゴウ」という法要に参加する習俗について、先行研究を踏まえながら考察する(本林)。重要無形民俗文化財である「気多の鵜祭」について、年占と位置づける観点がどのように登場したかを、古文書を網羅的に再検討する(干場)など、能登の宗教と民俗に関する事象あるいはその研究方法が新たに生成してきた事情に焦点を当てた。 著 者:由谷裕哉 編 定 価:¥2,500 発行日:2022.09.30 ISBN:978-4-86627-123-1 判 型:A5 頁 数:168 頁
-

石の説話
¥1,650
8世紀から19世紀まで71篇の出典により「闘う石」から「そばこ石」まで石にまつわる珍談奇談93話を集成し案文化した。2003年5月急逝の石像美術史研究家の遺著だが、出典には奇著も多いので集成された本書も奇著というべきか。 著 者:京田良志 定 価:¥1500 発行日:2003.10 判 型:四六判 頁 数:206 頁
-

孤村のともし火
¥1,320
1939~43年、飛騨山中を診療で廻った医師の三つの探訪記。加須良(白川村)では痛切な幼子の弔い話、山之村(阿曽布村)では民俗も探訪、杣が池(高根村)では伝説を詳しく紹介。ほかに民間療法と熊の膽の話。写真満載。 著 者:海野 金一郎 定 価:¥1200 発行日:2005.04.29 ISBN:978-4-903351-06-8 判 型:A5変判 頁 数:166 頁
-

神通川と呉羽丘陵 –ふるさとの風土–
¥4,400
飛騨国を発して越中を貫く神通川、そして呉羽丘陵。生い立ちから親しんできた著者の、文学作品と伝説、民俗学的・国語国文学的な考察を織り交ぜた壮大な歴史紀行(写真180葉)。無数の史的な小片が<<まほろば>>を織り上げる。 著 者:廣瀬 誠 定 価:¥4000 発行日:2003.9 判 型:A5判 頁 数:350 頁
-

越中怪談紀行
¥1,980
例えば、浮世の味気なきを感じた遊女が身を沈めた「池」が放生津沖の「海」中に今もあるという。 奇怪な仕掛けを持ち、庶民のうっ積した情念をみる怪談を集め、百年前の1914(大正3)年に連載された48話を現地探訪するカラー版。 著 者:桂書房 定 価:¥1800 発行日:2015.9.3 ISBN:978-4-905345-90-9 判 型:A5判 頁 数:156 頁
-

二人の炭焼・二人の紙漉
¥2,200
【第21回地方出版文化奨励賞】 昭和21年、 富山を振り出しに長野県栄村・群馬県東村と夫婦で遍歴、 30年で元山に戻る伝統の炭焼、 奥の深い技を披露する。 故郷のビルダン紙を再興した妻が難病に倒れるとその紙漉を受け継ぐ、 深く切ない夫婦の物語。 付・山口汎一「越中蛭谷紙」 著 者:米丘寅吉 定 価:¥2000 発行日:2007.2 ISBN:978-4-903351-26-1 判 型:A5判 頁 数:255 頁
-

おわらの記憶
¥3,080
富山市八尾町に伝わる民謡おわらは謎が多い。 そんなおわらの実像を、文献資料を基に調査研究。 明治から昭和初期までのおわらの変遷を紹介、おわらがどのように磨かれていったかを明らかにする。 資料編として豊富な資料を収録。 著 者:おわらを語る会 / 編 定 価:¥2800 発行日:2013.08 ISBN:978-4-905345-44-2 判 型:B5変判 頁 数:428 頁
-

有峰の記憶
¥2,640
昭和3年(1928)閉村、昭和35年ダム湖に水没した有峰村の歴史と民俗を網羅、分析する。 里に出た元村人の子孫に伝わる伝承と写真も掲載。 常願寺源流の奥深い山里に千年を生きてきた人々のことを深く知れば、いまの人々もきっと千年は生き延びられる。 --------------------------------------------- 著 者:前田 英雄 定 価:¥2400 発行日:2009.08.10 ISBN:978-4-903351-74-2 判 型:B5変判 頁 数:357 頁
-

千保川の記憶
¥3,080
【高岡開町400年記念出版】 砺波扇状地を貫流する大河であった千保川。 薪や米や塩を載せた長舟が行き交い、前田利長公の築城以来、幾万もの人生を映して流れ去った川水を呼び戻すような400点の写真が見もの、100人を越える地元の執筆者による華麗な文化史。 著 者:千保川を語る会 編 定 価:¥2800 発行日:2009.5 ISBN:978-4-903351-64-3 判 型:B5変判 頁 数:450 頁
-

山姥の記憶
¥2,200
深山に棲む山妖怪「山姥」に関する伝承は驚くほど多い。 室町初期成立の謡曲の舞台となった北陸道山中の上路や新潟・長野・飛騨・尾張・奥三河にまで伝承収集の範囲を広げ、金時伝承や機織り伝承、神話や花祭りとの関連を考察する。 著 者:斎藤泰助 定 価:¥2000 発行日:2001.2 ISBN:4-905564-26-3 判 型:B5変版 頁 数:198 頁
-

富山の祭り
¥1,980
魚津のたてもん、富山のさんさい踊り、八尾の風の盆、岩瀬・新湊・伏木・城端・高岡の曳山、砺波・福野の夜高、福岡のつくりもん―― 本書は12の章と8つのコラムからなる。祭礼の魅力を21人の研究者らが解説。 著 者:阿南透・藤本武編 定 価:¥1800 発行日:2018.03.04 ISBN:978-4-86627-045-6 判 型:A5判 頁 数:252 頁
-

とやまの石仏たち
¥3,080
人々の暮らしに寄り添い、守られてきた石仏。路傍にある文化財である。 富山県内の石仏を詳細に調査し記録。熱烈な郷土愛から生まれた渾身の一冊。 著 者:尾田武雄 定 価:¥2800 発行日:2008.3.3 ISBN:978-4-903351-16-2 判 型:B5変型判 頁 数:191 頁
-

北陸海に鯨が来た頃
¥2,200
明治初め突然に捕鯨を始める内灘・美川・日末の加賀沿海。定置網発祥の越中・能登では江戸中期から「専守防衛」の捕鯨が。見渡す限りの鯨群が日本海にあったことを実感する初の北陸捕鯨史。 「能州鯨捕絵巻」や遺品もカラー紹介。 著 者:勝山敏一 定 価:¥2000 発行日:2016.06.20 ISBN:978-4-86627-010-4 判 型:A5判 頁 数:237 頁
-

越中山河覚書Ⅰ
¥2,640
生活の変化とともに、その所在が忘れられつつある岩屋・ほら穴や岬を踏査し、その由来や伝承を取材。 また、多数の新旧の雪形を紹介。野生の生きものとも出会いの体験談も収録。 山国であり雪国ならではの富山を知る一書。 著 者:橋本 廣 定 価:¥2400 発行日:2002.4 判 型:B5変形判 頁 数:270 頁
-

富山湾 豊かな自然と人びとの営み
¥2,530
自然環境に適応し、歴史の中で形成された生活や生業、風土の魅力を26人の専門家が語る。 1:自然と地史 2:生態と人間 3:ネットワーク社会 4:文化と空間 5:信仰と民俗 6:持続社会に向けて 著 者:秋道智彌・中井精一 編 定 価:¥2300 発行日:2020.09.16 ISBN:978-4-86627-089-0 判 型:B5 頁 数:169 頁
-

富山なぞ食探検
¥1,760
雑煮に焼魚が入るのはどこ?新年に食べるのはブリ?サケ?一万円もするカキモチがあるって?66の郷土食一つ一つにプロフェッショナルのいることを紹介。もちろん美味の秘密を教えてくれる!孫子に贈る全カラー150頁。 著 者:読売新聞富山支局編 定 価:¥1600 発行日:2008.7 ISBN:978-4-903351-53-7 判 型:A5版 頁 数:203 頁
-

最古の富山県方言集
¥2,200
高岡新報掲載「越中の方言」(武内七郎) 大正5(1916)年6月から199回にわたって掲載され、富山県方言の総合的資料としては最古のもの。 本書の公刊により富山県方言に関するもっとも古い分布状況などが明らかになり、歴史的研究、言語変化に関する研究が今後大きく進展することが予想される。 見出し語数は延べ3,218語で、対象となる言葉は多岐にわたっており、また県内のことばの地域差や近隣の県との異同、社会階層とことばの関連にも言及されており、当時の富山県方言を知る上での貴重な資料といえる。 巻末に語彙索引もあり、100年ほど前の富山県方言をわかりやすく詳しく知ることが出来る。 編 者:髙木千恵 (代表)、水谷美保、松丸真大、真田信治 (財団法人新村出版記念財団刊行助成図書) 定 価:¥2000 発行日:2009.12 判 型:四六判 頁 数:352 頁
-

〈加賀料理〉考
¥3,080
加賀料理を藩主の御前料理に限定して、じぶ・燕巣・麩・豆腐・鱈・鮭・鯛・鯉について考察8編。そしてお抱え料理人・小島 為善(1816~93)の編著から公的な献立・作法を記した『真砂子集』、調理方法をまとめた『真砂子集聞書』を翻刻。 著 者:陶 智子 笠原 好美 綿抜 豊昭 編 定 価:¥2800 発行日:2009.4 判 型:A5判 頁 数:217 頁